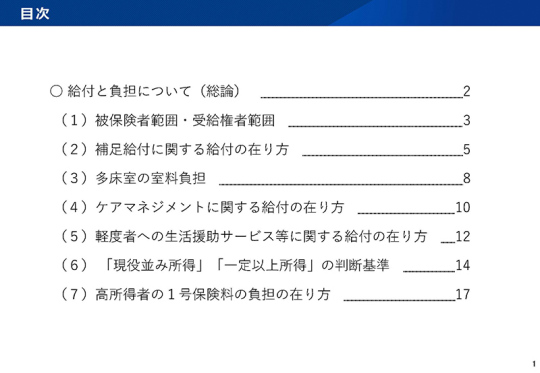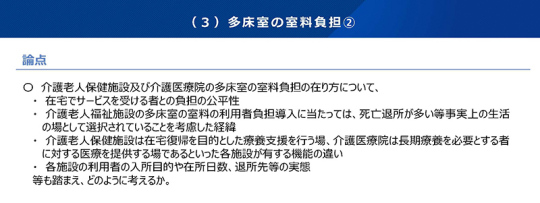「給付と負担」の論点で見解 ── 介護保険部会で橋本会長

介護保険制度の見直しに向けて「給付と負担」をテーマに議論した厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の橋本康子会長は、多床室の室料負担やケアマネジメントに関する給付、軽度者への生活援助サービスなどの論点について見解を述べた。
厚労省は10月31日、社会保障審議会(社保審)介護保険部会(部会長=菊池馨実・早稲田大学法学学術院教授)の第100回会合をオンライン形式で開催し、当会から橋本会長が委員として出席した。
厚労省は同日の部会に「給付と負担について」と題する資料を提示。「被保険者範囲・受給権者範囲」や「多床室の室料負担」、「ケアマネジメントに関する給付」など7項目について論点を示し、委員の意見を聴いた。
.
.
今後、給付費の伸びが見込まれる
今回の主なテーマである「給付と負担」は、前々回9月26日の会合に続いて2回目の審議となる。
厚労省の担当者は説明の冒頭、「既に何度も議論してご承知のことかと思うが、今後、給付費の伸びが見込まれる中で給付と負担のバランスを図りつつ、保険料、公費、利用者負担の適切な組み合わせによって制度の持続可能性を高めていくことが重要な課題と考えている」と述べた。
その上で、政府の「全世代型社会保障構築会議」で検討が進んでいることを紹介。「こうしたことを踏まえ、7つの論点について検討を行っていただきたい」と各項目の現状などを説明した。
.
医療保険制度との整合性を
7つの論点のうち「多床室の室料負担」について厚労省の担当者は、介護老人福祉施設の多床室の利用者負担を挙げ、「事実上の生活の場として選択されていることを踏まえ、個室と同様、光熱水費と室料の利用者負担を求めた。居宅系サービスとの負担の均衡を図るという観点で実施した」と経緯を説明した。
その上で、「多床室の室料負担の在り方について、(中略)死亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されていることを考慮した経緯(中略)等も踏まえ、どのように考えるか」と意見を求めた。
.
.
橋本会長は「理論的には正反対」と指摘。「家族の心理としては、医療は一時的で介護は長期にわたるので、一時的であるなら部屋代などは払ってもいいが、長期に渡るとなかなか難しい」とし、「医療保険制度との整合性を考えていただきたい」と述べた。詳しくは以下のとおり。
■ 被保険者・受給権者の範囲について
.
資料4ページの論点について、先ほど小林委員がおっしゃったように、受給者は高齢者だけではない。若者の中にも身体障害が残っている人もいる。リハビリでの入院期間が終わった後も非常に困難な状態になっている。そういう人も多くおられるので、そのあたりも考えていただきたい。
障害者は、医療や介護の費用に障害者手当などの給付をどんどん使うわけにはいかない場合もよくあるし、市町村によって仕組みが違うので、そのあたりのことも考えていただきたいと思っている。
若年者の場合は作業所などいろいろあるとはいうが、それは割と知的障害には手厚いところはあるのだが、身体障害に関しては希薄というか、なかなか利用できるところがないし、経済的にも困っているところが多いということを言わせていただきたい。
.
■ 多床室の室料負担について
.
介護保険料がすごく上がっていることはよくわかるし、生活の場であるということもよくわかるが、資料8ページ(多床室の室料負担①現状)にもあるように、「医療保険制度との関係も踏まえつつ」というところで、医療保険制度のほうは負担の公平性を見るだけではなくて、低所得者でも公平に医療が受けられるようにという意味があると思う。
そのため、50%は差額室料を取ってはいけない。たとえ個室であろうが、50%は差額室料は取れないことになっている。そういった点から考えると、施設においても公平に介護サービスを受けにくくなるのではないかと思う。そのあたりは医療保険制度との整合性を考えていただきたいと思っている。
また、利用者や患者、ご家族の心理としては、医療は一時的であることが多いのに対し、介護は長期にわたるので、一時的であるなら部屋代や居住費は払ってもいいが、長期に渡るとなかなか難しいということがある。そのため、理論的には正反対になってしまう。生活の場で長期になるから居住費をいただくという理論だが、利用する人から言えば、「長期になったら、お金はちょっと払えない」ということが実際にある。そういったことも考えていただきたい。
.
■ ケアマネジメントに関する給付について
.
実際に私どもの現場では、利用される本人ではなく家族が連絡をとってくる。そのときに、家族は入院している病院の医師やソーシャルワーカーに「どうしたらいいですか」と尋ねる。私どもは「ケアマネージャーさん、自治体に連絡してください」と説明する。その時点では家族の人はケアマネジメントの重要性を全く認識されていないので、利用者負担がかかってくると、やはり利用控えが少なからず起こってくるのではないかと思う。
そうなると、治療やケアの必要性などがよくわからない家族が考えて動いてしまうので、どうしても生活援助のほうへ流れてしまうことになりやすい。リハビリや認知症ケアとかいうことに費用が使われるということが減ってくるのではないかとも思う。
.
■ 軽度者への生活援助サービス等に関する給付について
.
要介護度1・2が3・4・5にならないようにしていくということ。そのような最も大事なところが要介護度1・2の軽度者への援助サービスというか、そのケアの在り方だと思う。とすれば、負のループにならないようにしてほしい。
そこがとても希薄というか、専門家が入っていないとなると、要介護度1・2でいられるはずなのに3・4にどんどん進んでしまう。それを阻止するためのサービスだと思う。そのため、特に認知症の人などは、専門職の介入と、それ以外のサービスというように分けて、専門職の介入というのを重要視するシステムを考えなければならないのではないか。
(取材・執筆=新井裕充)
2022年11月1日